釣りが好きで、魚を食べるのも好きな小学6年生の息子は、最近では自分で魚の卸屋に行き、その日の鮮魚を買ってくる。
この日はホウボウを仕入れ、親子で調理してみた。
ホウボウはこんな魚
ホウボウはホウボウ科に属する魚。大きいものは40センチにもなるが、この日のホウボウは30センチほど。胸鰭が大きく開き、羽のように見えた。
浮袋で「グーグー、ボーボー」という音を出すという。この音が由来で「ホウボウ」という名がついたと言われているそうだ。
なぜ、音を出すかというと、明確ではないが相手を驚かしたり、仲間に危険を知らせるためだとか。
生息位置は水深600メートル以浅の砂泥底。胸びれの一部が太く、昆虫の脚のように発達しており、これを動かして海底を歩く。
包丁を使ってさばいていく
今回は息子が一人で捌くのに挑戦。危ない部分のみサポートに入れるように、そばで見守る。
 三枚おろしから(撮影:栗秋美穂)
三枚おろしから(撮影:栗秋美穂)まずは三枚おろし。骨の上を切っていく。
最初は小刻みに包丁を入れていくと、尾に向かってスムーズに包丁が入る。
 骨を外していく(撮影:栗秋美穂)
骨を外していく(撮影:栗秋美穂)裏返して、同じように骨の上ギリギリに包丁を入れる。
このとき、底面は骨だけなので安定しないので、慎重にさばくこと。
 ひとまず柵取りができた(撮影:栗秋美穂)
ひとまず柵取りができた(撮影:栗秋美穂)上手に3枚に仕上がった。
皮を剥いだ際、その表面がキラキラしているほど鮮度がいい。
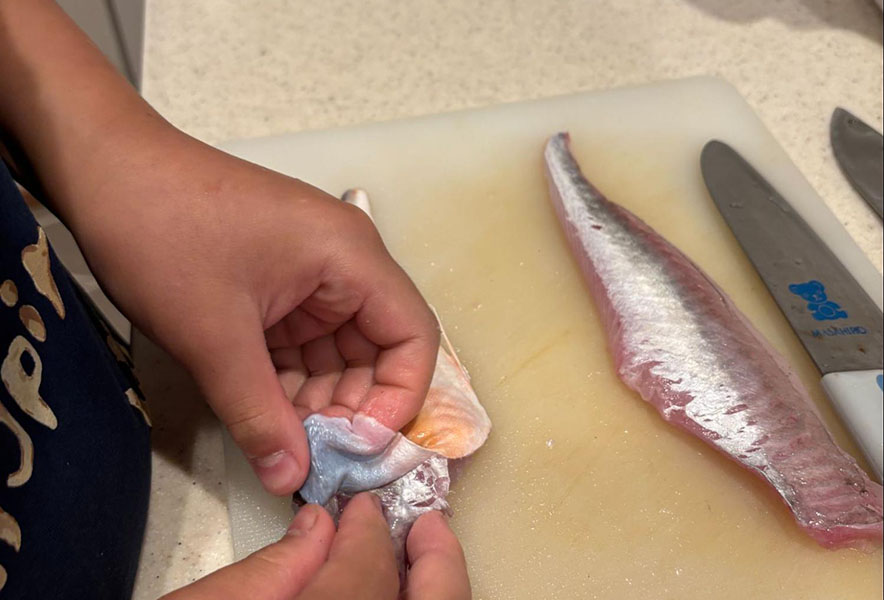 皮を剥いでいく(撮影:栗秋美穂)
皮を剥いでいく(撮影:栗秋美穂)身を削がないように、丁寧に皮を剥ぐ。中骨を抜こうとしたが硬く太く、普通のピンセットではダメだったので、ペンチを使った。
怪我無く息子ひとりで捌くことができたが、頭を落とすときなどは大きな力が必要だ。
また、包丁を扱うことは当然危険と隣り合わせ。お子さんが魚をさばくのに挑戦するときは、ぜひ近くで見守ってあげてほしい。
ホウボウの刺し身の完成!
斜めに削ぎ切りをして盛り付けると、白身の美味しい刺身が出来上がった。
 刺身の盛り合わせの完成(撮影:栗秋美穂)
刺身の盛り合わせの完成(撮影:栗秋美穂)皿に盛られた、いちばん上がホウボウである。共に捌いたアジよりも分厚かったのが印象的だ。
ホウボウは通年出回っている魚なので、今度は天ぷらにしてみようと思う。
自分ではなかなか釣れない魚たちであるが、こうして「命」をいただく経験をすることで、さらに魚への愛着、または海の環境問題にも思いは繋がっていく。
子どもと共に魚を捌き、それを食する──命の営みに直接触れる体験をしてみてはいかがだろうか。
(サカナトライター:栗秋美穂)
参考文献
本村浩之(2015)、学研の図鑑LIVE 魚、小学館
