人はなぜ、動物園や水族館に行くのでしょうか。また、園館でなくとも、休日に自然観察やキャンプ、登山、BBQなどを行う人も多いと思います。
それらは普段の衣食住には不要なもの。なぜ人々は、わざわざ余暇を水族館や自然観察などに費やすのか──。
その理由について科学的な側面から紹介し、またそれらを筆者の自然観察体験談に照らし合わせて考察していきます。
なぜ人は自然を求めるのか
かつての狩猟採集時代と比べると、現代の日本をはじめ多くの地域では暮らしが大きく豊かになり、衣食住に困らない人も増えてきました。
もちろん、世界には今も自然と密接に暮らす人々がいますが、都市生活を基準にすれば、危険が多い自然での生活は難しいと考えるのが自然でしょう。
 元日にキャンプをする筆者。なぜわざわざこんなことを……?(撮影:みのり)
元日にキャンプをする筆者。なぜわざわざこんなことを……?(撮影:みのり)しかし、現代も余暇をあえて自然の中で過ごす人が大勢います。
遠い山奥のキャンプ場で1泊する、標高何千メートルもある険しい山々を登頂する、溺れる可能性のある海中世界に潜りダイビングをする……そこまでいかなくとも、水族館や動物園を訪れ、生き物や自然を求める人は多数います。
これは一体なぜなのでしょうか?
「癒される・リフレッシュできるから」「生き物や自然が好きだから」という答えが一般的だとは思いますが、前述した長く危険な狩猟採集時代を考えれば、本能レベルで自然を嫌っていてもおかしくないはずです。しかし現実には本能レベルで自然や生き物を嫌う人はあまりいません。
その理由は「狩猟採集時代」にヒントがあります。
ヒトの脳は進化していない?
『ストレス脳』(著:アンデシュ・ハンセン/訳:久山葉子/発行:新潮社)などで有名なスウェーデンの精神科医アンデシュ・ハンセンは、ヒトの脳は「狩猟採集時代」からほとんど進化していないと主張します。
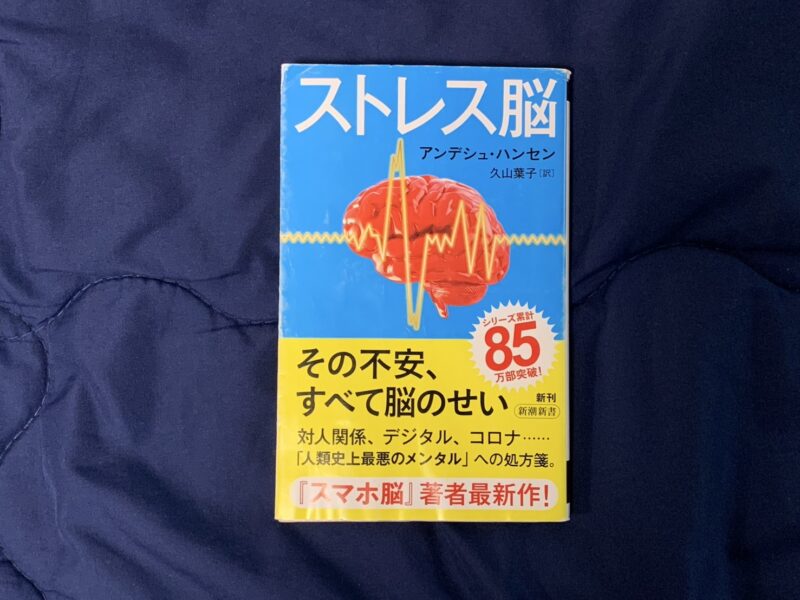 『ストレス脳』(著:アンデシュ・ハンセン/訳:久山葉子/発行:新潮社/撮影:みのり)
『ストレス脳』(著:アンデシュ・ハンセン/訳:久山葉子/発行:新潮社/撮影:みのり)ハンセン氏は、現代の情報化社会はここ数百年の間に発達したものに過ぎず、何万年もかけて進化した原始時代の脳を有するヒトがその社会に馴染めるはずがないと考察します。
ハンセン氏は精神科医なので、この主張を精神医学に照らし合わせて考察していますが、私はこの「ヒトの脳は原始のまま」という主張が、自然教育や水族館などにおいても当てはまるのではないかと考えます。
生き物を専門に認知する脳
そして、この分野について、動物行動学の面から研究・考察しているのが、公立鳥取環境大学学長の小林朋道氏です。動物行動学の専門家で、その対象を動物に限らずヒトにも定め、「なぜ人は自然や生き物に惹かれるのか」を調べています。
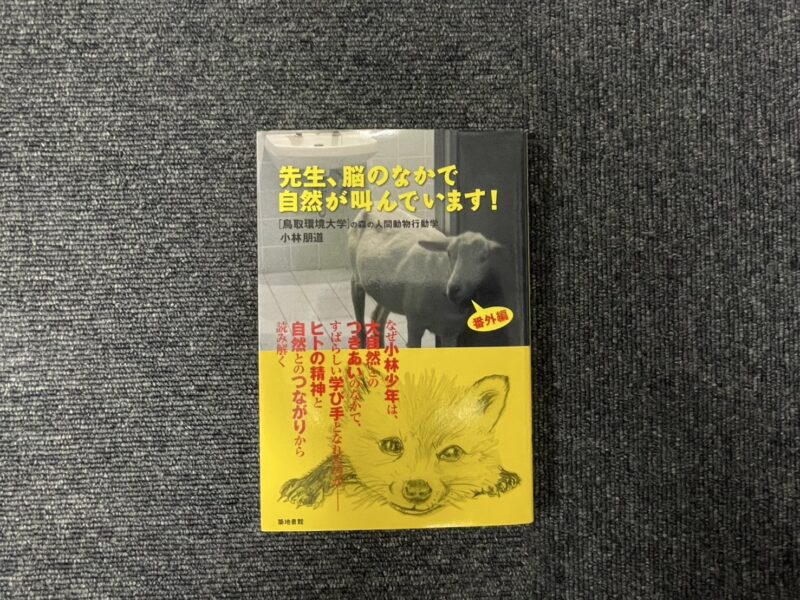 『先生、脳のなかで自然が叫んでいます![鳥取環境大学]の森の人間動物行動学』(著:小林朋道/発行:築地書館/撮影:みのり)
『先生、脳のなかで自然が叫んでいます![鳥取環境大学]の森の人間動物行動学』(著:小林朋道/発行:築地書館/撮影:みのり)小林氏は、ヒト(ホモ・サピエンス)は「生物」「物体(無生物)」「同種(ホモ・サピエンス)」といった異なる性質の情報に対応した脳の認知専門領域を内蔵していると主張。つまり、ヒトは生き物を専門に認知する脳の領域(生物認知専門領域)を有しているということです。
これはヒトが原始時代から何万年もかけて発達させた脳の領域で、小林氏によると、この「生物認知専門領域」は適切な自然からの刺激がなければ健全に発達しないといいます。
「生物認知専門領域」が何らかの原因で働かなくなった場合、無生物である傘やハサミ、スーパーマーケットの位置などは認知できても、イヌや魚、ウロコ、羽といった生物由来のものは認知できなくなってしまうのです。
言語能力が周囲の人々の言葉の入力を受けながら活性化するのと同じく、生物認知も周囲の自然や生き物からの刺激を受けないと活性化しないのです。
